「いつかは大型犬と暮らしたい」そう考えたとき、多くの人が憧れるのが、優しく穏やかなゴールデンレトリーバーではないでしょうか。
しかしその一方で、「ゴールデンレトリーバーを飼うのは大変」という声を聞き、後悔しないか不安に感じていませんか?
ネットで「飼ってはいけない10の理由」といった記事を目にしたり、共働きで飼うことの難しさ、やんちゃな子犬期には家がボロボロになるという、あるある話を見たりすると、家族に迎える決心が一歩踏み出せなくなるかもしれません。
また彼らの人を惹きつけてやまない優しい性格はなぜなのか、共に過ごせる時間を示す平均寿命や、かかりやすい病気について、事前に詳しく知っておきたいと考えるのは当然のことです。
この記事では、ゴールデンレトリーバーとの生活で直面するかもしれない大変な側面を包み隠さず解説すると同時に、それを遥かに上回る大きな魅力と、深い絆を育むためのヒントを余すことなくお伝えします。
あなたの疑問や不安を解消し、素晴らしいパートナーシップを築くための第一歩をサポートします。
- ゴールデンレトリーバーが大変と言われる具体的な理由
- 飼い主が後悔しやすいポイントとその対策
- 大変さの先にあるゴールデンレトリーバーの魅力
- 安心して迎えるために必要な準備と心構え
ゴールデンレトリーバーが大変と言われる理由
- ゴールデンレトリーバーを飼ってはいけない10の理由
- ゴールデンレトリーバーを飼い後悔するポイント
- ゴールデンレトリーバーあるあるから見る現実
- ゴールデンレトリーバーで家がボロボロになる?
- ゴールデンレトリーバーを共働きで飼う難しさ
- 毎日の散歩と運動量が想像以上に必要
ゴールデンレトリーバーを飼ってはいけない10の理由
輝く金色の被毛と、人懐っこい笑顔。
ゴールデンレトリーバーは理想的な家庭犬として世界中で愛されています。
しかし、その穏やかなイメージの裏には、飼い主の覚悟と努力を必要とする、大型犬ならではの現実が存在します。
「飼ってはいけない」という強い言葉が使われるのは、彼らの持つ特性が、飼い主のライフスタイルや住環境、経済状況によっては、手に余るほどの大きな負担となり得るからです。
憧れだけで迎えてしまうと、犬も人間も不幸になりかねません。
具体的にどのような点が大変なのか、一般的に言われる10の理由を深く掘り下げて見ていきましょう。
- 想像を絶する抜け毛の量と掃除の手間
ダブルコートの長毛種であるため、一年を通してかなりの量の毛が抜けます。特に春と秋の換毛期には、面白いほどごっそりと毛が抜け落ち、家中が毛だらけに。「掃除しても追いつかない」と嘆く飼い主は少なくありません。毎日のブラッシングと、こまめな掃除機がけは必須のルーティンとなります。アレルギー体質の方が家族にいる場合や、掃除に時間をかけられない方にとっては、深刻な問題となる可能性があります。 - 有り余る体力と、それに見合う運動量の確保
もともとハンターが撃ち落とした水鳥を回収する鳥猟犬として活躍していたため、その体力は並大抵ではありません。成犬になってもエネルギッシュで、多くの運動量を必要とします。毎日の散歩はもちろんのこと、時にはドッグランで思い切り走らせたり、ボール遊びをしたりと、エネルギーを発散させるための時間と工夫が不可欠です。体力と時間に余裕がないと、欲求不満から無駄吠えや破壊行動などの問題行動につながることがあります。 - 大型犬ならではの、決して安くない飼育費用
体が大きいということは、食費、医療費、ペット用品(ベッドやケージ、おもちゃなど)、トリミング代など、すべてにおいて小型犬よりも費用がかさみます。特に医療費は高額になりがちです。大手ペット保険会社アニコム損害保険株式会社の調査によると、大型犬の年間診療費は小型犬の約1.5倍にものぼるというデータもあります(出典:アニコム損保 家庭どうぶつ白書2023)。万が一の手術や長期治療に備え、ペット保険への加入や、十分な経済的準備が求められます。 - 天使の顔をした、子犬期の破壊行動
温厚で落ち着いた成犬のイメージとは裏腹に、子犬期は非常にやんちゃで好奇心旺盛です。特に歯の生え変わり時期(生後4ヶ月〜7ヶ月頃)には、口に入るものすべてをおもちゃと認識し、家具や壁、スリッパ、電気コードなど、あらゆるものを噛んで破壊してしまう「破壊魔」と化す可能性があります。この時期の適切なしつけと、噛んでも良いおもちゃを与えるなどの環境設定が非常に重要です。 - 寂しがりやで、分離不安になりやすい繊細な心
人と一緒にいることが大好きで、家族とのコミュニケーションを何よりも大切にする犬種です。そのため、長時間の留守番は大きなストレスとなり、飼い主への強い依存心から分離不安症を発症することがあります。分離不安になると、飼い主がいない間に延々と吠え続けたり、破壊行動や不適切な場所での排泄といった問題行動を引き起こすことがあります。 - 愛情表現?避けられない、よだれの多さ
個体差はありますが、比較的よだれが多い犬種としても知られています。特に食事や運動の前後、そして飼い主におねだりする時には、たくさんのよだれを垂らすことがあります。床や家具、時には飼い主の服がよだれで汚れることも日常茶飯事と覚悟しておく必要があります。 - そのパワーを制御するための、絶対不可欠なしつけ
基本的には非常に優しい性格ですが、成犬になると体重は30kgを超え、その力は相当なものです。興奮して人に飛びついたり、散歩中に強く引っ張られたりすると、大人の男性でもコントロールが難しくなります。子犬の頃から、社会性を身につけさせ、基本的なコマンド(おすわり、まて、など)や、人の横について歩く(ヒール)訓練を根気強く行うことが、安全で楽しい共生のために不可欠です。 - 犬種特有の、遺伝的にかかりやすい病気の存在
股関節形成不全や肘関節形成不全といった関節疾患、悪性腫瘍(がん)、アレルギー性皮膚炎など、犬種として遺伝的にかかりやすいとされる病気がいくつかあります。これらの病気は、治療が長期にわたったり、高額な医療費が必要になったりするケースも少なくありません。迎える前に、どのような病気のリスクがあるのかを把握しておくことが重要です。 - 必ず訪れる、老犬になった時の介護問題
大型犬であるため、老いて足腰が弱ると介護は大きな負担となります。体重があるため、寝たきりになった場合の床ずれ防止のための体位変換や、排泄の補助、動物病院への通院など、飼い主には相当な体力と精神的な覚悟が求められます。愛犬の最期まで責任を持つということは、この介護の問題と向き合うことでもあります。 - 心と体を満たす、十分な飼育スペースの確保
大型犬であるゴールデンレトリーバーが、室内でストレスなく快適に過ごすためには、ある程度の広さが必要です。体を伸ばしてゆったりと寝そべったり、おもちゃで遊んだりできるスペースを確保してあげる必要があります。庭があれば理想的ですが、基本的には室内で家族と共に過ごすことを好むため、狭い住環境での飼育は犬にとって大きなストレスになる可能性があります。
ゴールデンレトリーバーを飼い後悔するポイント
「こんなはずじゃなかった…」ゴールデンレトリーバーを家族に迎えた飼い主が、時にそう感じてしまうことがあります。
それは犬が悪いわけではなく、多くの場合、迎える前の理想と現実との間に大きなギャップがあることが原因です。
どのような点で後悔しやすいのか、具体的なポイントを知っておくことで、飼い主と愛犬双方の不幸なミスマッチを防ぐことができます。
① 抜け毛と掃除の手間が想像を絶していた
後悔の理由として圧倒的に多く聞かれるのが、この抜け毛の問題です。
「大型犬だから毛が抜けるのは分かっていたけど、ここまでとは…」というのが本音でしょう。
黒い服は着られなくなり、ソファやカーペットは常に毛で覆われ、掃除機をかけたそばからまた毛が落ちている、という状況は日常です。
食事の中に毛が入ってしまうこともあり、衛生面でストレスを感じる人もいます。
この終わりのない掃除との戦いに疲れ果て、後悔につながるケースが非常に多いのです。
② 医療費が経済的に大きな負担になった
ゴールデンレトリーバーはがんの発症率が高い犬種としても知られています。
元気だった愛犬が突然病に倒れ、高額な手術費や抗がん剤治療費に直面し、「ペット保険に入っておけばよかった」「経済的な覚悟が足りなかった」と後悔する飼い主は少なくありません。
またアレルギー性皮膚炎などで生涯にわたって定期的な通院や薬、療法食が必要になることも珍しくなく、継続的な医療費が家計を圧迫することもあります。
③ 自分の時間がほとんど持てなくなった
毎日の散歩、ごはんの準備、ブラッシング、部屋の掃除、そして何より愛犬とのコミュニケーション。
ゴールデンレトリーバーとの生活は、飼い主の時間と労力を多く必要とします。
これまで友人との食事や趣味、旅行に使っていた時間が大幅に犬中心の生活にシフトし、「自分の時間が全くなくなった」「どこにも自由に出かけられない」と感じてしまうことがあります。
特に犬を飼うのが初めての方や、仕事や育児で多忙な方は、この生活の変化の大きさに戸惑い、精神的に追い詰められてしまうことがあります。
これらの後悔は、決して特別なことではありません。
しかし迎える前に犬種の特性を正しく、そして深く理解し、自分のライフスタイルや価値観、経済状況と冷静に照らし合わせておくことで、その多くは乗り越えられる課題でもあります。
憧れだけでなく、現実を見据えた覚悟を持つことが何よりも重要なのです。
ゴールデンレトリーバーあるあるから見る現実
ゴールデンレトリーバーと暮らす飼い主たちが、思わず「うちも!」と頷いてしまうような共通の「あるある」行動。
これらは、この犬種の魅力と、時に飼い主を悩ませる大変さの両面をリアルに映し出しています。
愛らしくも、時にはちょっぴり困ってしまう、そんな彼らの日常の一コマを覗いてみましょう。
誰にでもフレンドリーすぎる「永遠のウェルカムモード」
ゴールデンレトリーバーは非常に社交的で、人間が大好きです。
その愛情は家族だけにとどまらず、散歩中に出会う人、宅配便の配達員、家に来たお客さんなど、すべての人に向けられます。
尻尾をちぎれんばかりに振り、満面の笑みで「遊ぼう!」と大興奮で飛びついてしまうことがよくあります。
この天真爛漫なフレンドリーさは最大の魅力ですが、犬が苦手な人や小さな子供、お年寄りには恐怖心を与えてしまう可能性も。
番犬としては全く期待できない、この「ウェルカムすぎる」性格を制御するためのしつけは、公共の場でのマナーとして必須です。
なんでも口に入れてしまう「歩く食いしん坊探知機」
食べ物への執着が非常に強く、常に何か美味しいものはないかと探している食いしん坊な子が多いのも特徴です。
テーブルの上に置いておいたパン、子供が落としたお菓子のかけらなどは、一瞬の隙に見事に消え去ります。
さらに問題なのが、散歩中の拾い食いです。
落ちているタバコの吸い殻やビニール片、時には石や木の実まで、何でも口に入れてしまう危険性があります。
誤飲や中毒は命に関わるため、飼い主は常に目を光らせ、食べ物の管理や拾い食いをさせない「ちょうだい」のコマンドを徹底して教える必要があります。
自分を小型犬だと思っている?「自覚なき巨体」
体重30kgを超える大きな体にもかかわらず、本人は自分のサイズを全く理解していないかのように振る舞います。
飼い主がソファに座っていると、当たり前のように膝の上に乗ろうとしてきたり、狭いスペースに無理やり入り込もうとしたりします。
甘えん坊な性格の表れで、その行動は非常に愛らしいのですが、その体重とパワーで飼い主が押しつぶされそうになることもしばしば。
この「自覚なき大型犬」っぷりは、多くの飼い主を笑顔にさせると同時に、時折軽い怪我をさせる原因にもなる、愛すべき「あるある」の一つです。
ゴールデンレトリーバーで家がボロボロになる?
「ゴールデンレトリーバーを飼うと家がボロボロになる」という噂は、残念ながら、特に子犬期においては現実のものとなる可能性が高いと言えます。
成犬の穏やかな姿からは想像もつかないかもしれませんが、エネルギーが有り余っている子犬期から若犬期(およそ2歳頃まで)は、小さな怪獣のようです。
この破壊行動には、犬なりの理由があります。
主な原因は、①運動不足による退屈やストレス、そして②歯の生え変わり(むず痒さ)に伴う「噛みたい」という本能的な欲求です。
有り余るエネルギーを適切に発散できず、噛む欲求を満たせるものが身近にないと、その矛先は家の中のあらゆるものに向かいます。
彼らの破壊対象は、飼い主の想像を超えて多岐にわたります。
- 家具の脚:テーブルや椅子の脚は、ちょうど良い高さと硬さで、格好の噛むおもちゃにされてしまいます。
- 壁紙や柱:部屋の角の部分は特に狙われやすく、気づいた時には壁紙が剥がされ、中の石膏ボードが見えていることも。
- スリッパや靴:大好きな飼い主の匂いがついているため、特にお気に入りのおもちゃにされがちで、無残な姿で発見されます。
- 電気コード:非常に危険です。噛みちぎってしまうと感電の恐れがあり、命に関わります。
- リモコンや本:留守番中に退屈しのぎで破壊され、重要な書類が紙吹雪になることもあります。
しかしこれは犬が悪いわけではなく、成長過程の一部です。
この破壊行動を最小限に抑え、人間と犬が快適に暮らすためには、以下の対策が非常に有効です。
破壊行動への具体的な対策
- 十分な運動と刺激:毎日の散歩でエネルギーを発散させるのはもちろん、ボール投げや知育トイ(中におやつを隠せるおもちゃ)を使って頭を使わせることで、心身ともに満足させます。
- 噛んでも良いおもちゃの提供:犬用の安全な噛むおもちゃを複数用意し、「噛んで良いもの」と「悪いもの」の区別を根気強く教えます。おもちゃは犬が飽きないように、時々種類を変えてあげると良いでしょう。
- 留守番の環境整備:犬が一人で過ごすスペースは、危険なものや噛まれたくないものを徹底的に片付けます。電気コードはカバーで保護し、届かない場所に配置するなどの工夫が必要です。サークルやケージを「安全で落ち着ける場所」として教えて活用する(クレートトレーニング)のも非常に有効です。
- 「噛む」ことへの一貫したしつけ:人の手や家具などを噛んだら、低い声で「いけない」と伝え、その場を離れて遊びを中断します。これを繰り返すことで、「これを噛むと飼い主さんがいなくなってしまう」と学習させます。
成犬になり、精神的に落ち着いてくれば破壊行動は自然と減っていきます。
しかし、子犬期は家がある程度傷つくことを覚悟し、壊されても良い環境を整えるくらいの心構えでいることが、飼い主の精神的な平穏にもつながるでしょう。
ゴールデンレトリーバーを共働きで飼う難しさ
現代社会において、共働き家庭で犬を飼うことは珍しくありません。
ゴールデンレトリーバーを迎えたいと願う共働き家庭も多いでしょう。
しかし結論から言うと、それは「不可能ではないが、相当な覚悟と工夫が必要」です。
最も大きな課題は、長時間の留守番による犬のストレスと、多忙な中で日々のケアに割く時間をいかに確保するかという点に尽きます。
ゴールデンレトリーバーは、人と共に働く犬として作出された歴史から、非常に寂しがりやで、家族と一緒に過ごすことを何よりも好む犬種です。
一般的なフルタイムで働く家庭の場合、通勤時間を含めると1日に10時間近く家を空けることになり、この長時間の孤独は犬にとって大きな精神的苦痛となり、前述の分離不安を引き起こす大きな要因となります。
また、体力的な問題も無視できません。
仕事で心身ともに疲れて帰宅した後でも、愛犬はエネルギー全開で「遊んで!」と要求してきます。
ここから最低でも30分以上の散歩に行き、部屋で遊び、ごはんの世話やブラッシングをするという毎日を、雨の日も風の日も、体調が悪い日でも続けなければなりません。
特に子犬期は、数時間おきのトイレのしつけや社会化のために、より多くの時間と手間がかかります。
共働き家庭でゴールデンレトリーバーと幸せに暮らすためには、以下のような具体的な協力体制やサービスの活用が不可欠です。
- 家族内での完全な協力体制:散歩、食事、しつけ、通院など、すべての役割を夫婦(家族)で明確に分担し、どちらか一方に負担が偏らないようにする。朝の散歩は夫、夜は妻、など具体的なルールを決めることが重要です。
- 柔軟な働き方の活用:夫婦の一方が在宅勤務やフレックスタイム、時短勤務などを活用し、物理的に犬が一人でいる時間を可能な限り短縮する努力が求められます。
- 外部サービスの積極的な利用:昼間に散歩や世話をしてくれるペットシッターや、他の犬と交流しながら日中を過ごせる犬の保育園(デイケアサービス)などを定期的に利用することも有効な選択肢です。
- 昼休みの一時帰宅:職場の許可が得られ、家が近い場合に限られますが、昼休みに一度帰宅してトイレをさせたり、少し遊んであげたりするだけでも、犬のストレスは大きく軽減されます。
「犬が好き」「癒されたい」という気持ちだけでは、共働きでの大型犬との生活は成り立ちません。
家族全員が「この子のために自分たちの生活を変える」という強い意志を持ち、具体的な計画を立てられるかどうかが、迎える前の重要な判断基準となります。
毎日の散歩と運動量が想像以上に必要
ゴールデンレトリーバーの心身の健康を維持し、問題行動を防ぐ上で、十分な運動は食事と同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。
彼らの祖先が、広大なスコットランドの原野を一日中駆け回り、撃ち落とされた水鳥を回収するという重労働を担っていたことを考えれば、その有り余る運動能力の高さは容易に想像できるでしょう。
一般的に、成犬のゴールデンレトリーバーに推奨される散歩時間は、1回あたり30分から1時間程度、これを1日に2回とされています。
しかし、これはあくまで健康維持のための最低ラインです。
特にエネルギーレベルの高い若い犬にとっては、これだけでは足りないこともしばしばあります。
重要なのは、運動の「量」だけでなく「質」です。
ただ単に飼い主のペースでアスファルトの上を歩くだけの散歩では、彼らの満足度は決して高くありません。
時には公園の芝生の上でロングリードを使って思い切り走らせたり、彼らの大好きなボール投げを取り入れたり、頭を使わせる「ノーズワーク(嗅覚を使ったゲーム)」を行ったりと、運動に変化と刺激を取り入れる工夫が求められます。
もしこの運動欲求が満たされないと、犬は溜まったエネルギーとストレスを別の形で発散させようとします。
- ストレスによる問題行動:無駄吠え、家具や壁を破壊する、自分の手足を執拗に舐め続けるといった行動に現れます。
- 肥満のリスク:消費カロリーが摂取カロリーを上回ることで肥満になり、股関節形成不全などの関節疾患を悪化させたり、心臓に負担をかけたりと、様々な病気の引き金となります。
- 心身の不健康:適度な運動は、犬の脳を刺激し、精神的な安定にもつながります。運動不足は、犬を無気力にさせ、うつ状態に似た症状を引き起こすこともあります。
夏の暑い日、冬の寒い日、そして雨や雪の日であっても、散歩は基本的に毎日必要です。
飼い主自身にも、どんな天候であっても愛犬のために外に出る体力と、それを継続する強い意志が求められるのです。
この日々の積み重ねこそが、ゴールデンレトリーバーとの信頼関係を築く土台となります。
ゴールデンレトリーバーの大変さを知った上での魅力
- なぜゴールデンレトリーバーは優しいのか
- ゴールデンレトリーバーの平均寿命と健康管理
- ゴールデンレトリーバーのかかりやすい病気
- しつけで賢さがより一層引き立つ
- ゴールデンレトリーバーの大変さを理解しよう
なぜゴールデンレトリーバーは優しいのか
ゴールデンレトリーバーが世界中の人々から「優しい犬」の代名詞として愛されているのには、偶然ではない、明確な理由が存在します。
その理由は彼らが歩んできた歴史と、その中で選択的に育まれてきた犬種としての特性に深く根ざしています。
人と協力するために「デザイン」された歴史
ゴールデンレトリーバーの歴史は、19世紀半ばのスコットランドに遡ります。
当時の貴族、ダッドリー・マーシュバンクス卿(後のトウィードマウス卿)が、自身の領地で行う鳥猟に最適な犬を作出しようとしたのが始まりです。
彼が求めたのは、①陸地でも水中でも効率的に獲物を回収できる能力、②ハンターの指示を的確に理解し、辛抱強く待機できる従順さ、そして最も重要な、③撃ち落とした獲物を歯で傷つけることなく、柔らかく口にくわえて運んでくる(ソフトマウス)性質でした。
この目的を達成するため、彼はウェービーコーテッド・レトリーバーを基礎に、現在は絶滅したツイード・ウォーター・スパニエルなどを交配させました。
この作出の過程で、人間に対して攻撃的であったり、神経質であったりする個体は繁殖から外され、穏やかで協調性が高く、人間を喜ばせることに喜びを感じる性質を持つ犬だけが意図的に選ばれてきたのです。
つまり彼らの優しさは、人間と共に働くパートナーとして「デザイン」された、最高の資質と言えます。
人の心を読み解く高い学習能力と知性
ゴールデンレトリーバーは、数ある犬種の中でもトップクラスの知性を持つとされています。
彼らはただ指示に従うだけでなく、飼い主の表情や声のトーンから感情を読み取り、どうすれば喜んでくれるかを常に考えて行動しようとします。
この高い共感能力と学習意欲が、彼らの優しさをさらに際立たせています。
この卓越した知性と穏やかな気質が認められ、彼らは猟犬としてだけでなく、盲導犬、聴導犬、介助犬といった身体障害者補助犬や、人の心に寄り添うセラピードッグとして、世界中の様々な場面で活躍しています。
彼らの優しさは、長年にわたる人間との共同作業の歴史の中で磨き上げられた、深い愛情と信頼関係の賜物なのです。
ゴールデンレトリーバーの平均寿命と健康管理
愛する家族の一員だからこそ、一日でも長く、健康でそばにいてほしいと願うのは当然のことです。
ゴールデンレトリーバーの平均寿命は10歳〜12歳とされており、大型犬としてはごく標準的です。
しかし、この寿命は飼い主の日々の健康管理によって大きく左右されます。
遺伝的な要因も大きいですが、適切なケアによって様々な病気のリスクを下げ、QOL(生活の質)を高めることが可能です。
健康寿命を延ばすために、特に重要となる3つの管理ポイントを見ていきましょう。
①食事管理と肥満予防:全ての基本
「ゴールデンは食いしん坊」と言われる通り、非常に食欲旺盛で太りやすい体質です。
そのため、食事管理は全ての健康管理の基本であり、最も重要なポイントと言っても過言ではありません。
肥満は万病のもとであり、特に体重が重い大型犬にとっては、股関節や膝などの関節に大きな負担をかけ、関節疾患を悪化させる最大の要因となります。
また心臓病や糖尿病、呼吸器疾患のリスクも高めます。
年齢(ライフステージ)、体重、活動量、そして体質に合った、質の良いドッグフードを、パッケージに記載された給与量を守って与えることが基本です。
人の食べ物や過剰なおやつは厳禁です。
常に愛犬の体を触り、肋骨がうっすらと感じられる程度の肉付きを維持することを心がけましょう。
②適度な運動:心と体の健康維持
前述の通り、毎日の運動は彼らにとって欠かせない日課です。
適度な運動は、肥満を防ぎ、全身の筋力を維持するだけでなく、ストレスを発散させ、精神的な安定をもたらす効果もあります。
ただし、年齢に応じた配慮が必要です。
骨や関節がまだ成長段階にある子犬期に、コンクリートの上でジャンプを繰り返すような過度な運動をさせると、関節を痛める原因になります。
逆に、シニア期(7歳頃〜)に入ったら、激しい運動は控えつつも、散歩の距離を短くして回数を増やすなど、無理のない範囲で運動を続けることが筋力低下を防ぎ、寝たきりの予防につながります。
③定期的な健康診断:病気の早期発見のために
犬は体の不調を言葉で訴えることができません。
またゴールデンレトリーバーは我慢強い性格の子が多いため、飼い主が異変に気づいた時には、すでに病気が進行してしまっているというケースも少なくありません。
そのため、症状がなくても定期的に動物病院で健康診断を受けることが、病気の早期発見・早期治療に繋がります。
若くて健康なうちは年に1回、シニア期に入ったら半年に1回の健康診断が推奨されます。
血液検査や尿検査、レントゲン検査、エコー検査などを定期的に行うことで、目に見えない体の中の変化を捉えることができます。
ゴールデンレトリーバーのかかりやすい病気
純血種であるゴールデンレトリーバーには、その犬種が持つ遺伝的な背景から、残念ながらかかりやすいとされる病気がいくつか存在します。
これらの病気について事前に正しい知識を持ち、日頃から愛犬の小さな変化に気づけるよう注意深く観察することが、早期発見と適切な治療への第一歩となります。
ここでは代表的な病気とその症状、注意点をまとめました。
| 病名 | 主な症状 | 注意点と対策 |
|---|---|---|
| 股関節形成不全 | ・歩くときにお尻が左右に大きく揺れる(モンローウォーク) ・後ろ足で同時に蹴るように走る(うさぎ跳び) ・散歩や運動、階段の上り下りを嫌がる ・座り方が不自然(横座りなど) | 遺伝的要因が大きい疾患ですが、子犬期の急激な体重増加や過度な運動、滑りやすい床での生活が症状を悪化させます。体重管理を徹底し、フローリングにはカーペットやマットを敷くなどの環境改善が非常に重要です。重症化すると外科手術が必要になる場合もあります。 |
| がん(悪性腫瘍) | ・体の表面や口の中にしこりができる ・原因不明の元気・食欲の低下 ・急激な体重減少 ・顎や首、脇の下、内股などのリンパ節が腫れる ・呼吸が苦しそう、咳が出る | ゴールデンレトリーバーは他犬種に比べてがんの好発犬種として知られており、死因のトップとも言われています。特にジャパンケネルクラブ(JKC)の犬種紹介ページでもその傾向が示唆されている通り、血管肉腫やリンパ腫、肥満細胞腫などが多く報告されています。日頃から全身を触ってしこりの有無をチェックする習慣をつけ、シニア期には定期的な健康診断(特にレントゲンやエコー検査)を受けることが早期発見の鍵となります。 |
| アトピー性皮膚炎 | ・体を頻繁にかく、床にこすりつける ・足先や指の間、脇、内股、顔周りなどを執拗に舐める ・皮膚の赤み、ブツブツ、脱毛、色素沈着 ・外耳炎を繰り返す | ハウスダストや花粉、食物などに対するアレルギー反応で起こる皮膚炎です。完治が難しく、生涯にわたる付き合いが必要になることも多い病気です。獣医師の指導のもと、内服薬や外用薬による治療、食事管理、薬用シャンプーによるスキンケアなどを組み合わせて症状をコントロールしていきます。 |
| 外耳炎 | ・耳をしきりに掻く、頭を激しく振る ・耳から異臭がする(甘酸っぱい、腐敗臭など) ・耳垢が異常に増える(黒、黄土色など) ・耳を触られるのを嫌がる | 湿気がこもりやすい垂れ耳の構造上、細菌やマラセチア(真菌の一種)が繁殖しやすく、外耳炎を起こしやすい犬種です。アレルギーが根本的な原因となっていることも少なくありません。予防には、定期的な耳掃除で耳の中を清潔に保つことが大切ですが、やりすぎは逆に耳を傷つけるので注意が必要です。 |
| 胃拡張・胃捻転症候群 | ・吐こうとするが何も出ず、えずきを繰り返す ・大量のよだれを垂らす ・お腹がパンパンに膨れる ・落ち着きがなく、苦しそうにウロウロする | 胸の深い大型犬に起こりやすい、緊急性の極めて高い病気です。胃がガスで膨れ上がり、ねじれてしまうことで血流が止まり、数時間で命を落とす危険があります。食後すぐの激しい運動が引き金になりやすいと言われています。食事は1日2回以上に分け、食後は最低でも1〜2時間は安静にさせることが最も重要な予防策です。疑わしい症状が見られたら、一刻も早く夜間救急対応の動物病院を受診する必要があります。 |
※ここに記載されている情報は、獣医学的な診断や治療に代わるものではありません。
愛犬の健康状態に少しでも不安や異常を感じた場合は、自己判断せず、必ず速やかに獣医師の診察を受けてください。
しつけで賢さがより一層引き立つ
ゴールデンレトリーバーは、全犬種の中でもトップクラスの賢さと、人を喜ばせたいという強い意欲を持つ犬種です。
この素晴らしい特性は、飼い主が愛情を持って適切なしつけを行うことで、ダイヤモンドのように磨かれ、一層輝きを増します。
彼らは学ぶことが大好きで、しつけは単なる訓練ではなく、愛犬との絆を深めるための最高のコミュニケーションツールとなります。
しかし、その賢さと体の大きさがゆえに、しつけを怠ると「賢いいたずらっ子」になり、そのパワーで飼い主が手に負えなくなってしまう危険性も秘めています。
特に重要なのが、人間社会で問題なく暮らしていくための基礎を作る、子犬期の「社会化」です。
犬の社会化期は、一般的に生後3週齢から12〜16週齢頃までと言われています。
この感受性の高い時期に、家族以外の人や他の犬、車や掃除機の音、様々な場所など、世の中にある多くのものに触れさせ、ポジティブな経験を積ませることが非常に重要です。
この時期に適切な社会化ができないと、成犬になったときに過度な臆病さや恐怖心から、吠えや攻撃性といった問題行動につながることがあります。
ワクチンプログラムが終わったら、積極的にパピークラス(子犬のしつけ教室)などに参加するのも良いでしょう。
また、日常生活における基本的な服従訓練(おすわり、まて、ふせ、おいで、ちょうだい など)は、愛犬の安全を守り、共に快適に暮らすために不可欠です。
ゴールデンレトリーバーのしつけでは、以下の点を心掛けることで、彼らの学習能力を最大限に引き出すことができます。
- 褒めて伸ばす(陽性強化トレーニング):ゴールデンレトリーバーは褒められることが大好きです。何か正しいことができたら、大げさなくらいに褒め、おやつや遊びといったご褒美を与えることで、「これをすると良いことがある」と楽しく学習していきます。力で押さえつけたり、厳しく叱責したりする方法は、彼らのデリケートな心を傷つけ、信頼関係を損なうだけです。
- 一貫性のある態度:家族全員でしつけのルールを統一することが非常に重要です。「ソファに乗ってはいけない」というルールなら、誰一人として例外を認めてはいけません。コマンド(指示の言葉)も統一し、犬が混乱しないようにします。
- 短時間集中型のトレーニング:犬の集中力は長くは続きません。長時間の訓練は犬にとっても飼い主にとっても苦痛になります。5分から10分程度の短いトレーニングセッションを、遊びの延長として1日に何回か行うのが最も効果的です。
力が強く体重もあるため、特に人への「飛びつき」、散歩中の「引っ張り癖」、命に関わる「拾い食い」の防止については、子犬の早い段階から根気強く、徹底して教え込む必要があります。
賢い彼らは、飼い主が愛情と一貫性をもってリーダーシップを発揮すれば、必ずその期待に応え、誰からも愛される素晴らしいパートナーとなってくれるでしょう。

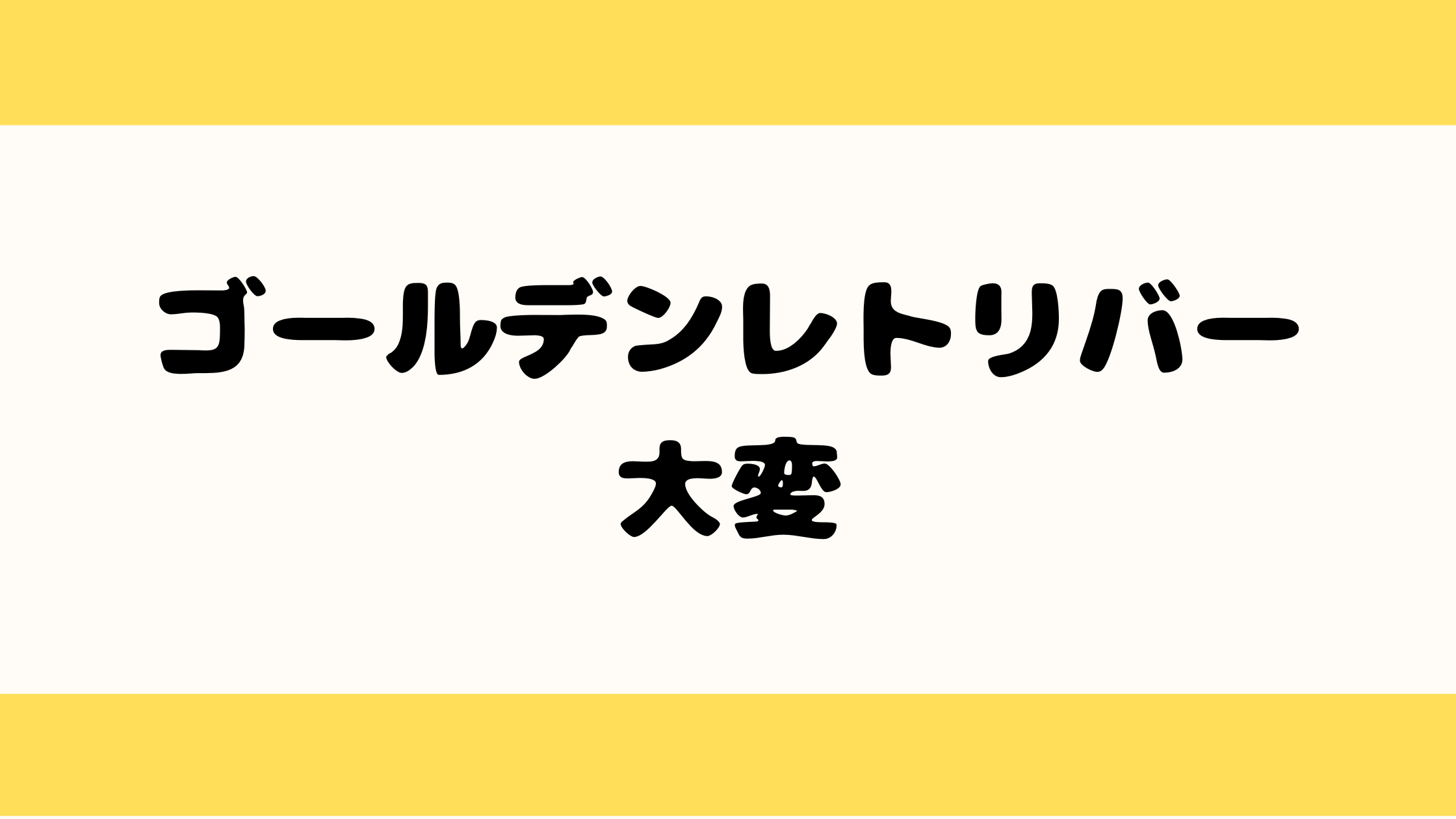
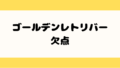
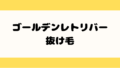
コメント